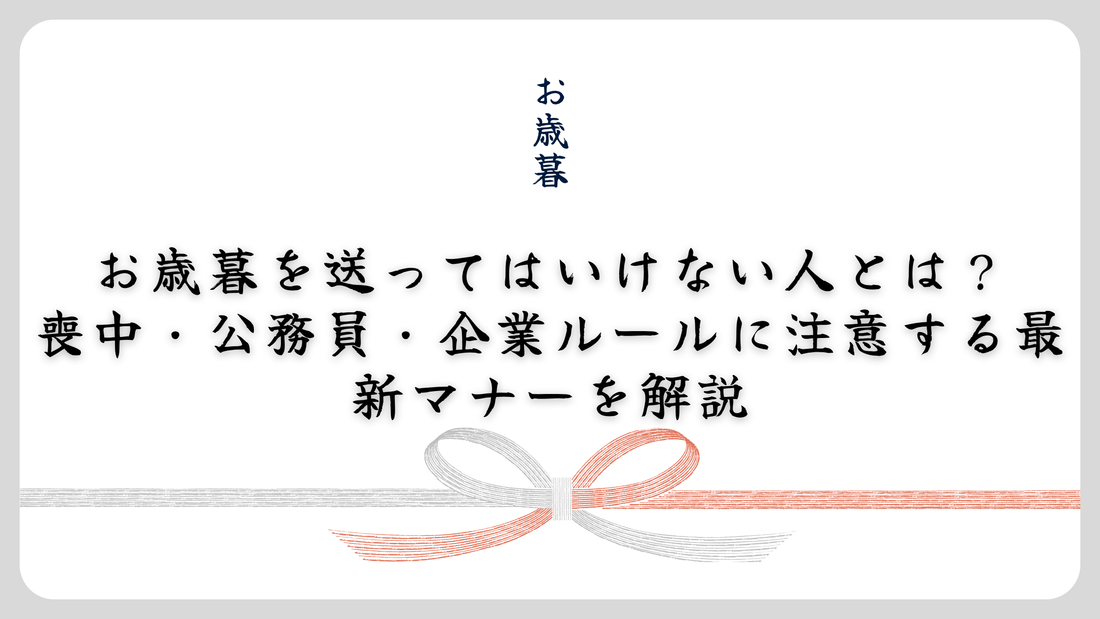
お歳暮を送ってはいけない人とは?喪中・公務員・企業ルールに注意する最新マナーを解説
WANTO編集部お歳暮は日頃の感謝を形にしたもので、基本的には好意的な文化です。しかし、相手の立場や状況によっては、贈らないほうが良いとされるケースも存在します。
この記事では、お歳暮を贈るのを控えるべき人やケースをわかりやすく解説します。
お歳暮を贈ってはいけない人
国家公務員および地方公務員は、国家公務員倫理法や地方公務員法により、利害関係者からの金品の受領が原則禁止されています。
特にお歳暮は、金品の提供に該当するため、たとえ個人的な関係でも、仕事上で関わりがある場合は贈ってはいけません。
その他の贈り物を控えるべき職業や立場
公務員以外でも、職務上の立場や組織規定によって贈答を控えるべき場合があります。以下のような職種は、個人での受け取りを禁止していることが多いので注意が必要です。
- 医師・看護師など医療従事者(患者からの贈答は禁止の病院が多い)
- 教師や保育士など教育関係者
- 銀行・証券など金融機関の担当者
- 警察官などの公的職務従事者
これらは法律上に禁止されているものではなく、あくまで職務の公平性やトラブル防止のための内部ルールです。贈る前に、相手の職場の方針を確認すると良いでしょう。
虚礼廃止の企業社員への贈り物は控えるのがマナー
虚礼廃止(きょれいはいし)とは、形式的な挨拶や贈答をやめるという企業方針です。最近では、大企業を中心にこの取り組みが拡がっており、会社単位でお歳暮・年賀状のやりとりを禁止していることがあります。
社員個人に贈っても社内ルールに違反する形になれば、かえって相手に迷惑をかけてしまうので、注意しましょう。取引先の企業や、社員宛に贈りたい場合には事前に確認することをおすすめします。会社によってはホームページなどに記載している場合もあります。
故人やその遺族宛のお歳暮は控える
相手のことを思い贈るお歳暮ですが、故人宛に送るのは控えることが望ましいです。遺族に対してもタイミングや表現を誤ると心情を傷つけかねないため、慎重に対応する必要があります。
喪中の場合はどうする?基本マナーと対応策
お歳暮は祝い事ではないため、喪中の期間でも贈って差し支えないとされています。
ただし、故人を偲ぶ意味で特に慎むべきとされる、忌中(きちゅう)の期間中は、贈るのを控えるのが一般的なマナーです。
忌中が明けた後であれば、喪中であってもお歳暮を贈ることは問題ありません。
- 忌中(きちゅう):亡くなってから四十九日(49日)まで
- 喪中(もちゅう):通常、亡くなってから一年間
喪中の場合のお歳暮マナーについては以下の記事をごらんください。
【喪中の御歳暮マナー】何を送る?御礼状は?失礼にならない贈り方とマナーを解説
<相手が喪中>喪中に贈る際は白無地の「かけ紙」で簡素に
喪中の方へお歳暮を贈る場合は、紅白の水引や「御歳暮」の文字は避けましょう。
- かけ紙:白無地または「寒中御見舞」「御伺」など
- のし:付けないのが一般的
包装もできるだけ華美なものは避け、控えめなデザインが好まれます。
<自分が喪中>お歳暮が届いたらお礼状で感謝を伝えよう
喪中でお歳暮をいただいた場合、故人宛でもお礼を伝えることがマナーです。形式は簡単で構いませんが、感謝と喪中である旨を伝えることで、今後の信頼関係の維持につながります。
お歳暮をやめる代わりに感謝を伝える方法
お歳暮の贈答をやめたいと思っても、贈る相手が年長者、取引先、目上の方などの場合は、贈らないことがかえって失礼なのではと感じるケースもあります。
そういった場合には寒中見舞いに切り替えたり、手紙で状況を伝えるなど、状況に応じて感謝の気持ちを表す手段を使いましょう。
手紙やメッセージカードで気持ちを届ける
心のこもった一筆は、お歳暮以上に印象に残ります。形式ばらず、感謝や近況報告などを添えたメッセージを送ることで好印象につながります。
寒中見舞いや新年のあいさつギフトへの切り替え
喪中対応が必要なときなどタイミングが合わない場合は、お歳暮ではなく1月7日〜2月初旬に届ける寒中見舞いや年始のあいさつ品に切り替えても問題ありません。表現も「お見舞い」になるため、喪中の方への贈答として適しています。
お歳暮文化の変化と現代の贈らない選択肢
感謝の気持ちを伝える手段として、古くから習慣になっているお歳暮ですが、近年、贈らない選択をする人も増えています。
博報堂生活総研の調査(2024年)によると、「お歳暮を毎年贈っている」と回答した人は全体の約19%に留まり、10年前より15%ほど減少しています。その背景には、価値観の多様化や贈答文化の見直しなどがあり、形式よりも実質重視の傾向が高まっていることがあげられるでしょう。
参考:博報堂生活総合研究所
SNSやメールなど新しい感謝の伝え方が増加
現在はデジタル化が進み、メールやSNSで感謝を伝えることが一般的になってきました。これも一つの新しいマナーの形であり、贈らないことが失礼ではない時代になってきています。
こうした相手との関係性を大切にしつつ、時代に合った贈り方を選ぶことが、真の心配りといえるでしょう。
お歳暮マナーを理解して心からの感謝を伝えよう
お歳暮は、日ごろの感謝を伝える日本ならではの美しい文化ですが、相手の立場や状況によっては、贈らないことが思いやりになることもあります。公務員や虚礼廃止の企業関係者、喪中の方など、マナーや法的制限を理解したうえで、適切な対応を心がけましょう。
また、時代とともに、感謝の伝え方も多様化しています。贈り物にこだわらず、手紙や言葉で感謝を伝える柔軟な姿勢こそが、現代にふさわしいお歳暮マナーといえるでしょう。心を込めた感謝が、相手との関係をより深めてくれるはずです。












