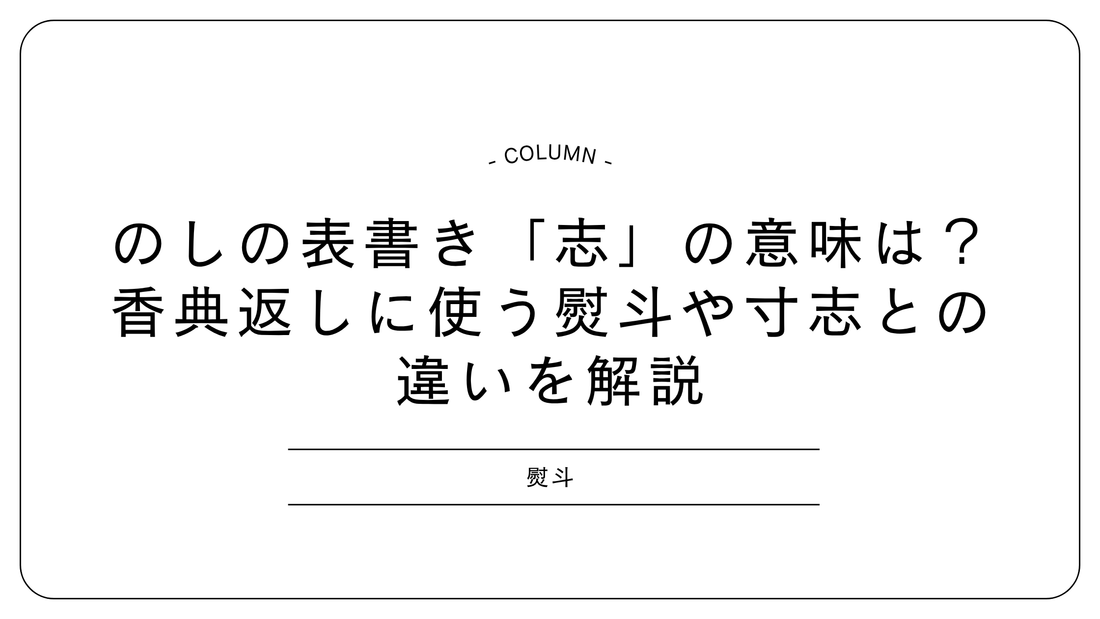
のしの表書き「志」の意味は?香典返しに使う熨斗や寸志との違いを解説
WANTO編集部香典返しの「のし(掛け紙)」に書かれる「志(こころざし)」。この言葉には、どんな意味があるかご存知でしょうか。
志には、香典や弔意を寄せていただいたことへの「心ばかりの感謝の気持ち」が込められています。
本記事では、志の正しい意味から失礼にならないための書き方、水引の選び方といった基本マナーまでわかりやすく解説します。
香典返しに使う「志」の意味とは?
香典返しののし紙に書く「志(こころざし)」は、故人への弔意に対する感謝の気持ちを込めた言葉です。「心ばかりのお返しです」という控えめな表現で、相手への敬意と感謝を丁寧に伝えます。
また、「志」は宗教や宗派を問わず使用できるため、仏式・神式・キリスト教式のいずれの香典返しにも適しています。
のし紙に「志」を書くときの基本マナー
弔事での表書きには、文字の位置・色・水引の選び方など、細やかな心配りが大切です。ここでは、香典返しにふさわしい書き方と掛け方の基本を紹介します。
表書きの位置と名前の入れ方

「志」の文字は水引の結び目の真上に書きます。名前は、水引の下に「鈴木家」のように「姓+家」とするか、喪主の氏名を記載します。
※内部リンク:「熨斗 連名 順番」
文字の色は「薄墨」か「濃墨」
文字の色は、贈る時期によって使い分けます。
通夜や葬儀の香典袋の文字の色は薄墨が一般的です。一方、四十九日の後に送る香典返しの掛け紙は濃墨(黒インク)が無難です。地域や慣習で薄墨を用いる場合もあるため、迷うときは現地の葬儀社に確認しましょう。
のし飾りのない掛け紙を選ぶ

香典返しに使うのは、のし飾りが印刷されていない掛け紙です。のしはもともとお祝い事の縁起物であり、弔事には適しません。
水引は「結び切り」を選ぶ

「二度と繰り返さないように」との意味を込めて、水引きは「結び切り」を選びます。色は、地域によって次のように使い分けます。
| 黒白の結び切り | 仏事全般で使用される基本的な形式 |
|---|---|
| 黄白の結び切り | 関西地方を中心に七七日忌後の香典返し(満中陰志)では、黒白の水引ではなく、黄白の水引を使うケースが多い |
【図解】のしの結び切りとは?蝶結びとの違い、結婚祝い・お見舞いでの使い方を解説
品物への掛け方

掛け紙を品物に掛ける際は、目的によって使い分けます。
| 内のし | 品物の箱に直接掛け紙をかけ、その上から包装紙で包む方法。 配送時に掛け紙が汚れるのを防げる |
|---|---|
| 外のし | 品物を包装紙で包んだ上から掛け紙をかける方法。 手渡しの際に表書きが見えるため、目的をはっきり伝えられる |
法事の熨斗(のし)のマナー・書き方とは?宗派・地域別の違いもまとめて解説
【宗教・地域別】「志」以外の表書きと掛け紙の選び方
宗教や地域によって、掛け紙のデザインや表書きの言葉に違いがあります。ここでは、仏式・神式・キリスト教式それぞれの特徴を見ていきましょう。
仏式
仏式では、白黒5本の結び切りに蓮の花の絵柄が入った掛け紙を使います。蓮は極楽浄土を象徴する花であり、仏式のときのみ選ばれる柄です。また、関西地方では四十九日の忌明けに行う香典返しを「満中陰志(まんちゅういんし)」と呼び、表書きに記載する風習があります。
神式・キリスト教式
神式では、五十日祭や三十日祭を忌明けとしてお返しをします。表書きには「志」のほか、次のような言葉も用いられます。
- 偲び草
- 五十日祭
キリスト教式には仏式のような「忌明け」はありません。カトリックでは30日目の追悼ミサ以降、プロテスタントでは1カ月後の召天記念日以降にお返しをします。
表書きには、次のような言葉が使われます。
- 志
- 偲び草
- 感謝
- 御礼
※内部リンク:「のし 表書き(一覧記事)」
「志」と間違えやすい言葉
「志」と似た言葉はいくつかありますが、使う場面や意味が異なります。ここでは、香典返しで混同しやすい言葉をまとめて紹介します。
寸志(すんし)
「寸志」は、「ほんの気持ち」という意味を持つ言葉です。目上の人が目下の人に渡す際に使う表現であり、香典返しには適していません。弔事で使用すると、相手に対して失礼にあたります。
満中陰志(まんちゅういんし)
「満中陰志」は、西日本でよく使われる表書きです。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 満 | 満ちる |
| 中陰 | 死後四十九日までの期間 |
| 志 | 感謝の気持ち |
四十九日の忌明け後に香典返しとして使う言葉であり、葬儀直後には使いません。時期を間違えると失礼にあたるため注意しましょう。
忌明志(きめいし)
「忌明志」は、四十九日が過ぎたあとの忌明けに感謝の気持ちを表す言葉です。
意味としては「満中陰志」とほぼ同じですが、京都を中心とした地域でよく使われます。なお、四十九日法要を繰り上げる場合は、のし紙の表書きを「忌明志」ではなく「志」とするのが適切です。
粗供養(そくよう)
「粗供養」は、葬儀や法要でお世話になった方への感謝を表す言葉です。「粗」にはへりくだった意味があり、喪主や施主が参列者に向けて使う表現です。参列者が自分から贈る際には使用しません。あくまで主催側(遺族側)が用いる言葉です。
偲び草(しのびぐさ)
「偲び草」は、故人を偲ぶ気持ちを品物に代えて贈るという意味があります。「志」とほぼ同じ意味を持ちますが、神式やキリスト教式で使われる言葉です。言葉選びに迷った場合は、宗教を問わず使える「志」を選ぶと安心です。
茶の子(ちゃのこ)
「茶の子」は、もともと「お茶うけに添えるささやかな品」という意味があります。葬儀や法事では香典返しのことを指す地域表現として使われています。
主に中国・四国・九州地方で見られる言葉で、「志」と同じく感謝の気持ちを伝える意味を持ちます。
香典返しのタイミングと渡し方
香典返しは、忌明けにあたる四十九日法要のあとに贈るのが基本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈る時期 | 四十九日法要の翌日から一週間以内 |
| 方法 | 直接手渡す、または郵送する |
| のし紙 | のし飾りなし。表書きに「志」または地域に合わせた言葉を使用する |
| 添えるもの | お礼状を同封し、感謝の気持ちを伝える |
郵送する場合は、のし紙をかけた品物にお礼状を添えるのがマナーです。手渡しの際には、感謝の言葉を添えるとより丁寧な印象を与えられます。
「志」の意味を正しく理解して失礼のない香典返しを
香典返しで使う「志」には、香典や弔意を寄せてくれた方への感謝の気持ちが込められています。
- 「志」は宗教や宗派を問わず使える表書き
- 書く位置は水引の上、名前はその下に記す
- 時期によって「薄墨」と「濃墨」を使い分ける
- 掛け紙は「のし飾りなし」で、黒白または双銀の結び切りを選ぶ
- 四十九日後にお礼状を添えて贈る
「志」の意味を理解し、心のこもった香典返しで感謝を伝えましょう。












