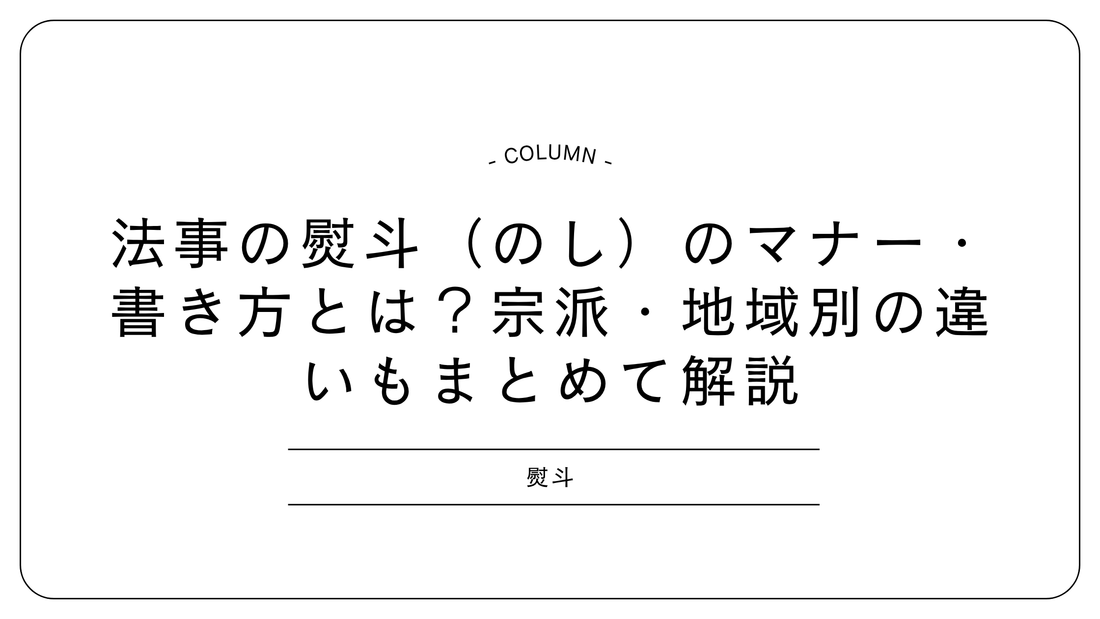
法事の熨斗(のし)のマナー・書き方とは?宗派・地域別の違いもまとめて解説
WANTO編集部法事の贈り物(お供え・返礼品)を用意する際、掛け紙の選び方に迷ってしまうことはありませんか。弔事(ちょうじ)では、お祝いごとで使う“のし付きの紙”ではなく、のしを省いた掛け紙を使うのが基本です。
この記事では、お供えや香典返しなど、シーン別に正しい掛け紙のマナーを解説します。はじめての方でも安心して準備できるよう、宗派や地域ごとの違いも紹介します。
法事の贈り物の正しい掛け紙の選び方

法事の贈り物には熨斗(のし)は付けません。ここでいう「のし」とは、右上にある細長い熨斗飾りのことを指します。熨斗飾りはお祝いに用いる縁起物のため、弔事では避けるのがマナーです。
法事では、のし飾りのない掛け紙を使います。一般的には「のし紙」と呼ばれていますが、正しくは「のしを省いた掛け紙」となります。
のし紙と掛け紙の違いは次のとおりです。
| 種類 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| のし紙 | お祝い事(結婚・出産など) | 右上にのし飾りがある |
| 掛け紙 | 法事・葬儀などの弔事 | のし飾りの付いていない無地のもの |
掛け紙は、贈り物を丁寧に包み、感謝や供養の気持ちを伝えるためのものです。弔事用では、水引の色や結び方、表書きの言葉にそれぞれ決まりがあるので注意してください。
法事で掛け紙が必要な場面
法事の掛け紙は、主に次の3つの場面で掛け紙を使います。
1.お供え物
法要にお菓子や果物などを持参する場合は、表書きは「御供(ごくう)」とします。
2.返礼品
法要に参列した方やお供えをいただいた方へのお礼として贈る品です。返礼品は法要当日にお渡しします。表書きは「志」または「粗供養」とします。
3.香典返し
香典をいただいた方に感謝の気持ちを伝える贈り物です。四十九日(忌明け)を過ぎてから贈ります。表書きは「志」とします。
【早見表】法事の表書き一覧
法事では、贈る側(香典や供物を渡す人)と、返す側(施主や遺族)で表書きが異なります。いずれの場合も、のし飾りのない掛け紙に、黒白または双銀の結び切りの水引を選びます。ただし地域によっては、黄白の結び切りを用いるケースもあります。
贈る側(参列者)が使用する表書き
この表は、通夜・葬儀や法要に参列する際に、「金銭や品物(お供え物)を渡す側」が使用する表書きです。
| 用途・目的 | 表書き | 主な対象 | 備考/宗派による違い |
|---|---|---|---|
| 品物:法要や命日に供える | 御供(ごくう) | お供え物(品物)の掛け紙 | 時期や宗派を問わず、品物を贈る際に最も一般的です。 |
| 金銭:通夜・葬儀に持参(四十九日前) | 御霊前(ごれいぜん) | 香典袋 | 仏式で一般的ですが、浄土真宗では使用しません。宗派不明の場合も使用できます。 |
| 金銭:四十九日以降の法要に持参 | 御仏前(ごぶつぜん) | 香典袋/不祝儀袋 | 仏式で四十九日法要以降に使用します。故人が仏になったと考えられています。 |
| 金銭:神式での弔事全般 | 御玉串料(おんたまぐしりょう) | 香典袋/不祝儀袋 | 神式で使用します。「御神前」「御榊料」「御弔料」も使用可。 |
| 金銭:キリスト教式での弔事全般 | 御花料(おはなりょう) | 不祝儀袋/白無地封筒 | キリスト教式で使用します。カトリックでは「御霊前」も可ですが、宗派不明なら「御花料」が安全。 |
返す側(施主/喪主)が使用する表書き
この表は、遺族・施主が香典や供物へのお礼として品物を返す際に使用する表書きです。
| 用途・目的 | 表書き | 地域・時期の慣習例 | 備考/適用宗教 |
|---|---|---|---|
| 全般のお返し(時期・宗教問わず) | 志(こころざし) | 全国的に使いやすい | 宗派を問わず使用でき、迷った場合に安心です。 |
| 四十九日後の返礼(忌明け) | 忌明志(きあけこころざし) | 関東地方などで使用 | 喪が明けたことを丁寧に伝える意味合いがあります。 |
| 四十九日後の返礼(主に関西) | 満中陰志(まんちゅういんし) | 関西地方中心 | 四十九日(中陰)の期間が満ちたことを意味します。一周忌以降の法事では使用しません。 |
| 四十九日後の返礼(中国・四国・九州の一部地域) | 茶の子(ちゃのこ) | 中国・四国・九州の一部地域 | 香典返しや法要の引き出物として使われます。 |
| 法要当日・即日返し | 粗供養(そくよう) | 関西や中国・四国・九州地方の一部 | 法要当日の引き出物や返礼品として使われます。 |
| 神式・キリスト教 | 偲び草(しのびぐさ) | 神式・キリスト教などで使用。 | 故人を静かに偲ぶ気持ちを伝える表現です。 |
| 神式・キリスト教 | 御礼(おんれい) | 宗教色を避けたい場合 | 生前や葬儀時にお世話になった方への感謝として使われます。 |
宗派や地域によって慣習が変わる場合もあるため、実際に使用する際には事前に確認すると安心できます。
法事にお供え物を渡すときのマナー
お供え物を渡す際のマナーを確認しましょう。
表書きの書き方

お供え物を渡す場合は、時期や宗派を問わず表書きに「御供(ごくう)」と書きます。
【香典を渡す場合】 ・仏式:四十九日までは「御霊前」、四十九日後は「御仏前」または「御佛前」
※浄土真宗では四十九日前でも「御仏前」を使用する ・神式:「御玉串料」や「御神前」 ・キリスト教式:「御花料(おはなりょう)」 ※キリスト教式では、水引のない白無地の封筒か十字架やユリの花が描かれたものを使います。
名入れは、下段に贈り主の名前を記入します。個人で贈る場合はフルネーム、連名なら立場や年齢が上の方の名前を右に書きましょう。
水引は黒白または双銀の結び切りが一般的です。関西など地域によっては黄白を用いる地域もあります。
お供え物の掛け紙は「内のし」で贈る
内のしとは、品物に掛け紙をかけてから包装紙で包む方法です。控えめで丁寧な印象を与え、弔事には適しています。
ただし、葬儀当日などで直接手渡す場合は、表書きが見えるように「外のし」にします。
渡し方・贈るタイミングの注意点
お供え物は、「法要の前日」または「当日の午前中」までに届くように手配します。
持参する場合は、施主(主催者)の方に「御仏前にお供えください」と一言添えて手渡します。自分で祭壇にお供えするのは避けましょう。
香典返しや返礼品を贈るときのマナー
香典返しや法要当日の返礼品(粗供養)を贈るときも、掛け紙の使い方には決まりがあります。掛け紙・表書き・水引を正しく選び、失礼のない形で届けましょう。
返礼品の相場は、もらった香典額の3分の1から半額(半返し)程度が目安となります。
表書きの書き方

香典返しの表書きは「志(こころざし)」と書きます。宗派を問わず使えるため、先方の宗派がわからず迷ったときにも安心できます。
関西地方では「志」の代わりに、「満中陰志(まんちゅういんし)」を使う地域もあります。これは四十九日を「中陰」と呼ぶ風習に基づいた表現で、四十九日(忌明け)の香典返しに使用されます。
法要当日に参列者へお渡しする品には「粗供養(そくよう)」と書くのが適切です。九州地方では、「茶の子(ちゃのこ)」という表書きを使うこともあります。
名入れは、下段に施主(喪主)の姓のみ、またはフルネームを記します。「〇〇家」のように、姓に「家」をつけても問題ありません。
掛け紙と水引の選び方
香典返しや返礼品には、のし飾りのない弔事用の掛け紙を使います。水引は黒白または双銀の結び切り。地域によっては黄白の水引を用いる場合があります。
迷ったときは、葬儀社や仏具店などに確認すると安心できます。
渡し方・贈るタイミングの注意点
香典返しは四十九日(忌明け)を過ぎた頃に郵送または手渡しで贈るのが一般的です。法要後1週間以内、遅くとも2週間以内が目安です。
故人が成仏したとされる節目である「忌明け」に、「無事に法要を終えました」という報告と感謝の気持ちを伝える意味があります。
法要当日の返礼品(粗供養)は、会食後にお礼の言葉を添えて渡すか、受付でスタッフに預けておくとスムーズです。郵送する場合は、お礼状を添えるとより丁寧な印象になります。
法事の掛け紙マナーを確認して丁寧な気持ちを伝えよう
法事で使う掛け紙には、故人を偲び、支えてくれた方々へ感謝を伝える意味があります。 表書きや水引の種類など、細かな違いはあっても、最も大切なのは「気持ちを丁寧に伝えること」です。
弔事では、お祝いの「のし飾り」を付けず、落ち着いた色合いの掛け紙を選びましょう。表書きは、宗派を問わず使える「志」や「御供」を選べば間違いがありません。
法事の贈り物に迷ったときは、この記事で紹介した早見表をぜひ参考にしてください。












