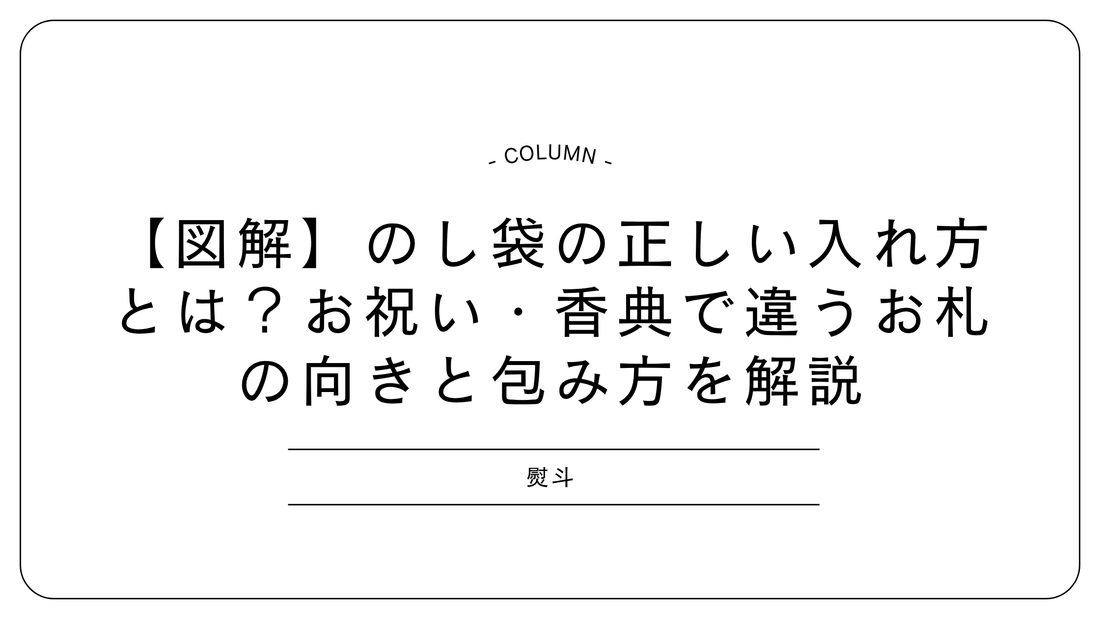
【図解】のし袋の正しい入れ方とは?お祝い・香典で違うお札の向きと包み方を解説
WANTO編集部結婚式に呼ばれたけれど「ご祝儀袋のお金の入れ方、これで合ってる?」と不安になったり、急な訃報で「香典のお札の向きは気にするべき?」と慌てたりした経験はありませんか。
のし袋に関するマナーは、お祝い事(慶事)とお悔やみ事(弔事)で、お札の向きから包み方まで正反対になるため、知らずにいると失礼にあたることにもなります。
この記事では、図解を交えながら、のし袋の正しいお金の入れ方をわかりやすく解説します。いざという時に慌てないよう、基本のマナーをしっかり身につけましょう。
のし袋のお札の正しい入れ方
結婚式などのお祝い事には縁起を担ぐマナーが多くあり、ご祝儀袋へのお札の入れ方や包み方もその一つです。また、弔事の香典についても、お札の向きや枚数など、正しい入れ方が決まっています。
上包みと中包み(中袋)とは
のし袋は、「上包み」と「中袋」または「中包み」がセットになっています。

- 上包み(外袋):のし袋の一番外側の包み。表書きや名前を記載する部分
- 中袋:お札を直接入れる封筒のこと。金額や住所を記入する欄があるタイプもある
- 中包み:半紙などを折ってお札を包むもの。中袋が付いていない場合に使用する
中袋が付属していない場合は、奉書紙や半紙で中包みを作っても構いません。
お祝い(慶事)とお悔やみ(弔事)の違い一覧
| 項目 | 慶事(お祝い事) | 弔事(お悔やみ事) |
|---|---|---|
| お札の種類 | 新札を用意する | 使用感のあるお札を使う |
| お札の向き | 肖像画がある面を表にし、上向きに入れる | 肖像画がある面を裏にし、下向きに入れる |
| 上包みの折り方 | 下の折り返しを上にかぶせる(上向き) | 上の折り返しを下にかぶせる(下向き) |
お札の枚数のマナー
結婚祝いでは「割り切れる=縁が切れる」を連想させるため、偶数枚は避けるのが一般的です。また、慶事・弔事ともに「死」や「苦」を連想させる4枚や9枚は避けるのがマナー。金額だけでなく、枚数にも気を配りましょう。
【お祝い】ご祝儀袋へのお金の入れ方
結婚祝いや出産祝いなど、お祝いの気持ちを伝える際の正しいマナーを紹介します。
お札の向きは「表・上向き」にして入れる
お祝い事には、前もって準備していたことを示すため、折り目のない新札を用意するのがマナーです。

- お札の肖像画がある面(表)を、中袋の表面に向けます。
- 中袋に入れたとき、肖像画が上にくるように揃えます。
上包みは「下→上」の順で幸運を招く
中袋を上包みで包む際は、「たとう折り」という折り方にします。幸せが舞い込み、それを受け止められるように、という願いが込められています。
- 上包みを広げ、中央に中袋を置きます。
- 左→右 の順で、中袋を包み込むように折ります。
- 下側を上に折り上げます。
- 最後に上側を下に折り下げ、下の折り返しに重ねます。
最終的に、裏側の折り返しが「上向き」(下の折り返しが上に見える状態)になっていればOKです。
【お悔やみ】香典袋へのお金の入れ方
お通夜やご葬儀など、お悔やみの気持ちを示す際の作法です。お祝い事とはすべて逆になるので注意しましょう。
お札の向きは「裏・下向き」にして入れる
香典では「突然の訃報に、急いで駆けつけた」という気持ちを示すため、新札は避けるのがマナーです。もし手元に新札しかない場合は、一度真ん中で軽く折り目をつけてから使いましょう。

- お札の肖像画がない面(裏)を、中袋の表面に向けます。(=顔を伏せるという意味合い)
- 中袋に入れたとき、肖像画が下にくるように揃えます。
中袋がないタイプの香典袋は、のし袋に直接同じ向きでお札を入れましょう。
上包みは「上→下」の順で悲しみを流す
香典袋の上包みの折り方は、ご祝儀袋とは逆です。「悲しみや不幸が流れ去るように」という意味が込められています。
- 上包みを広げ、中央に中袋を置きます。
- 左→右 の順で折ります。
- 上側を下に折り下げます。
- 上側の折り返しを最後に下側にかぶせます。
最終的に、裏側の折り返しが「下向き」(上の折り返しが上に見える状態)になっていればOKです。
法事の熨斗(のし)のマナー・書き方とは?宗派・地域別の違いもまとめて解説
のしの表書き「志」の意味は?香典返しに使う熨斗や寸志との違いを解説
持ち運ぶ際は「袱紗(ふくさ)」に包むのが正式マナー
ご祝儀袋や香典袋をそのまま鞄に入れるのはNG。汚れや水引の崩れを防ぎ、相手への丁寧な気持ちを示すために、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。
慶事と弔事で色と包み方を使い分ける
袱紗は用途によって使う色が異なります。紫色の袱紗は慶弔両用で使えるため、一枚持っておくと便利です。
| 用途 | 色 | 包むときの開き方 |
|---|---|---|
| 慶事(お祝い) | 赤・朱・桃などの暖色系 | 右開き |
| 弔事(お悔やみ) | 灰色・藍・緑などの寒色系 | 左開き |
| 慶弔両用 | 紫色 | 慶事は右開き、弔事は左開き |
布タイプのほか、最近は金封型・爪付き・台付きなど、折らずに挟むだけの便利なタイプも人気です。
袱紗の包み方
袱紗とは、ご祝儀袋や香典袋を包んで保護する布のことです。汚れや折れを防ぐ実用的な役割と、丁寧に贈り物を扱うという気持ちの象徴の両方を兼ねています。
慶事の包み方
- 袱紗をひし形になるように開いて置きます。
- 袱紗の中央からすこし左にご祝儀袋をのせます。
- 袱紗を左→上→下→右の順で畳みます。
- はみ出た部分を折り込み、形を整えます。
弔事の包み方
- 袱紗をひし形になるように開いて置きます。
- 袱紗の中央からすこし右に香典袋をのせます。
- 袱紗を右→上→下→左の順で畳みます。
- はみ出た部分を折り込み、形を整えます。
【シーン別】渡し方・郵送のマナー
最後に、受付での渡し方や、参列できない場合の郵送マナーについても確認しておきましょう。
手渡しの場合
受付では、まず袱紗からのし袋を取り出します。そして、相手から見て正面になる向きにして、手渡します。
- 慶事:「本日は誠におめでとうございます」と笑顔でお祝いの言葉を添えます。
- 弔事:「この度はご愁傷様でございます」と静かにお悔やみの言葉を述べます。
郵送の場合
やむを得ず参列できない場合は、必ず現金書留で郵送します。
- 慶事:お祝いのメッセージを添え、式の1週間前~前日までに届くように送ります。
- 弔事:お悔やみ状を添え、喪主宛に送ります。タイミングは、通夜や葬儀に間に合わなければ、後日落ち着いた頃でも構いません。
正しいマナーで大切な気持ちを伝えよう
のし袋のお金の入れ方は複雑に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえれば簡単です。
【お祝い事のポイント】
- 新札を、表向き・上向きに入れる
- 上包みの裏は下側が上(上向き)
- 暖色系の袱紗で右開きに包む
【お悔やみ事のポイント】
- 旧札を、裏向き・下向きに入れる
- 上包みの裏は上側が下(下向き)
- 寒色系の袱紗で左開きに包む
一つひとつの作法には、相手を思いやる心が込められています。この記事が、あなたの丁寧な気持ちを伝える一助となれば幸いです。












