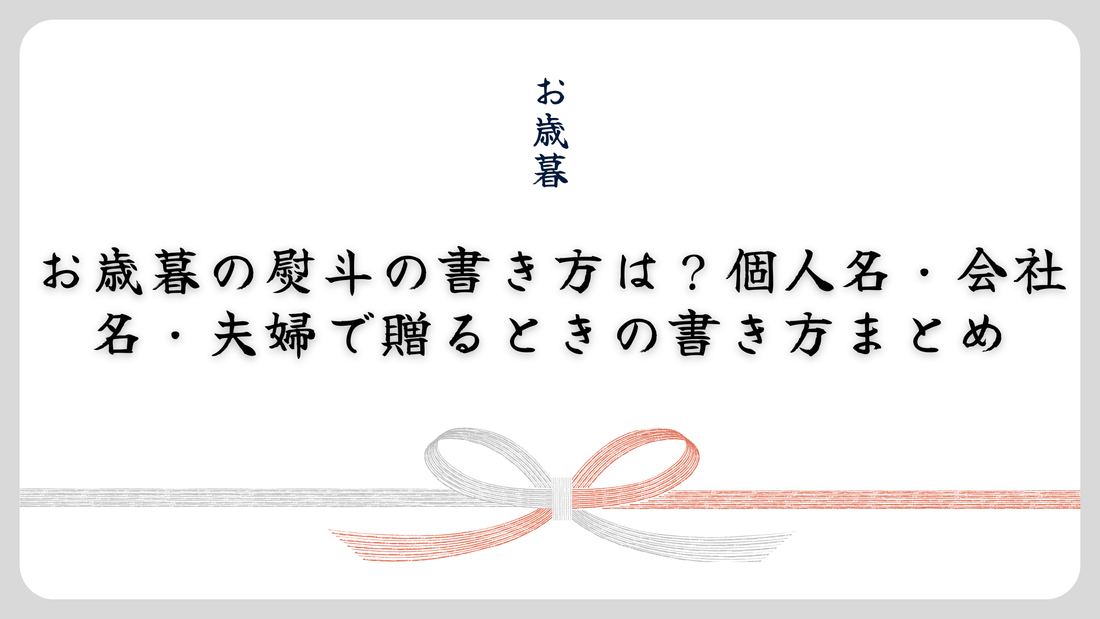
【2025お歳暮】お歳暮の熨斗(のし)の書き方は?個人名・会社名・夫婦で贈るときの書き方まとめ
WANTO編集部お歳暮は、品物選びだけでなく贈り方のマナーも大切です。中でも熨斗(のし)は、一年の感謝を丁寧に伝えるために欠かせないものです。しかし、「どう書くのが正しいの?」と迷うことも多いのではないでしょうか。 この記事では、お歳暮の熨斗に関する基本ルールから名入れのパターンまで、見本付きでわかりやすく解説します。
お歳暮を贈るときの熨斗の見本

熨斗とは、のし紙の右上にある六角形の飾りのことです。その起源は「慶事に贈る酒の肴(さかな)」に由来するといわれています。
古来より、祝儀の際には酒と共に肴が贈られており、特に鮑(あわび)は長寿や繁栄の象徴として珍重されていました。この鮑を薄く剥いで引き伸ばし、乾燥させたものが「熨斗鮑(のしあわび)」と呼ばれ、「伸ばす=永続・発展」の縁起を込めて贈り物に添えられていました。
つまり、熨斗を添えることには、「長寿を願っています」「心を込めた贈り物です」という、相手への敬意と祝福の気持ちが込められているのです。
お歳暮の熨斗|押さえておきたい5つの基本マナー
ここでは、熨斗の基本マナーを5つのポイントにわけて紹介します。
1.表書きは「御歳暮」にする
水引の結び目の上に書く言葉を「表書き」といいます。お歳暮の場合は「御歳暮」と書くのが一般的です。
2.水引は「紅白蝶結び」を選ぶ
お歳暮の熨斗には、紅白の蝶結び(花結び)の水引を使います。蝶結びは「何度でも結び直せる」ことから、「何度繰り返しても良いお祝い事」に用いられます。毎年贈るお歳暮にぴったりの結び方です。 ※結婚祝いなどで使う「結び切り」は一度きりのお祝いに使うものなので、間違えないよう注意しましょう。
3.熨斗のかけ方は「内熨斗」と「外熨斗」どちらでも可
熨斗のかけ方には「内熨斗」と「外熨斗」の2種類あります。どちらを選んでもマナー違反ではありませんが、シーンによって使い分けるとよりスマートです。

内熨斗
贈り物にのし紙をかけ、その上から包装紙で包む方法です。配送中にのし紙が汚れたり破れたりするのを防げるため、宅配で贈る場合におすすめです。
外熨斗
贈り物を包装紙で包んだ上からのし紙をかける方法です。贈り主や贈答の目的が一目でわかるため、持参して手渡しする場合に適しています。
4.「短冊のし(簡易のし)」でも問題ない
最近は、品物に直接貼り付ける「短冊のし(短冊熨斗)」も広く使われています。宅配での利用やカジュアルな贈り物に便利で、基本のマナーを守った形として問題ありません。ただし、改まった相手や大切な取引先に贈る場合は、通常ののし紙を選ぶ方が安心です。
5.【要注意】生ものを贈る場合は熨斗をつけない
お歳暮で鮮魚や精肉などを贈る場合、熨斗飾りのない「かけ紙」を使いましょう。 熨斗の由来が「鮑(生もの)」であるため、贈り物自体が生ものの場合は意味が重複してしまうからです。ハムなどの肉を加工したものや鰹節なども熨斗をつける必要はありません。
【パターン別】名入れの書き方見本
水引の下には、贈り主の名前を表書きより少し小さめに書きます。書き方を間違えると失礼にあたるので、基本のルールを押さえておきましょう。
個人で贈る場合

個人で贈るときは、誰からの贈り物かが分かるように名前をフルネームで書きます。名字だけでも意味は通じますが、フルネームの方が丁寧な印象になります。
夫婦で連名にする場合

夫婦で連名にする場合は、右側に夫、左側に妻の名前を記します。名字は夫の名前のみに付け、妻は名前だけを書きます。
会社名や肩書を入れる場合

法人で贈る場合は、水引の下部に代表者の名前を書き、名前の右側に会社名を入れます。会社名は名前よりも小さく書きます。
3名までの連名なら表に贈り主全員の名前を書く

友人や同僚など3名までの連名で贈る場合は、全員の名前を記載します。右側から目上の人順に書き、役職などがなければ五十音順で書きます。
連名で代表の名前のみを入れる場合

4名以上になる場合は、代表者1名の名前を中央に書き、その左下に「他一同」と書き添えます。全員の名前は、別紙に書いて品物に同封するのがマナーです。
お歳暮で迷うポイント|相手が喪中の場合はどうする?
お歳暮は、お祝い事ではなく日頃の感謝を伝える贈り物です。そのため、相手が喪中であっても、お歳暮を贈ること自体はマナー違反にはあたりません。 ただし、ご家族を亡くされて間もない時期は、相手も落ち着かない日々を過ごされているかもしれません。特に四十九日を過ぎるまでは贈るのを控えた方が良いでしょう。
【喪中の御歳暮マナー】何を送る?御礼状は?失礼にならない贈り方とマナーを解説
【最も丁寧な方法】時期をずらし「寒中御見舞」として贈る
相手への配慮を示す最も丁寧な方法は、お歳暮の時期をずらし、年が明けてから「寒中御見舞」として贈ることです。
- 贈る時期:松の内(1月7日頃)が明けてから、立春(2月4日頃)まで
- 表書き:「寒中御見舞」または「寒中御伺」(目上の方へは「寒中御伺」がより丁寧です)
- のし紙:通常の紅白蝶結びの熨斗紙を使います
どうしても年内に贈りたい場合の対応
年内にお歳暮として贈りたい場合は、お祝いの印象を与えないよう配慮します。
- のし紙:紅白の水引や熨斗飾りがついていない、シンプルなかけ紙(白無地の奉書紙や短冊)を選びます。
- 表書き:通常通り「御歳暮」とします。
まとめ

今回はお歳暮の熨斗について解説しました。大切なポイントは以下の3つです。
- 水引は「紅白蝶結び」を選ぶ
- 相手が喪中の場合は配慮が必要
- 名入れはパターンに合わせて正しく書く
この記事で紹介したマナーを参考に、一年の締めくくりにふさわしい、心のこもったお歳暮を贈りましょう。












