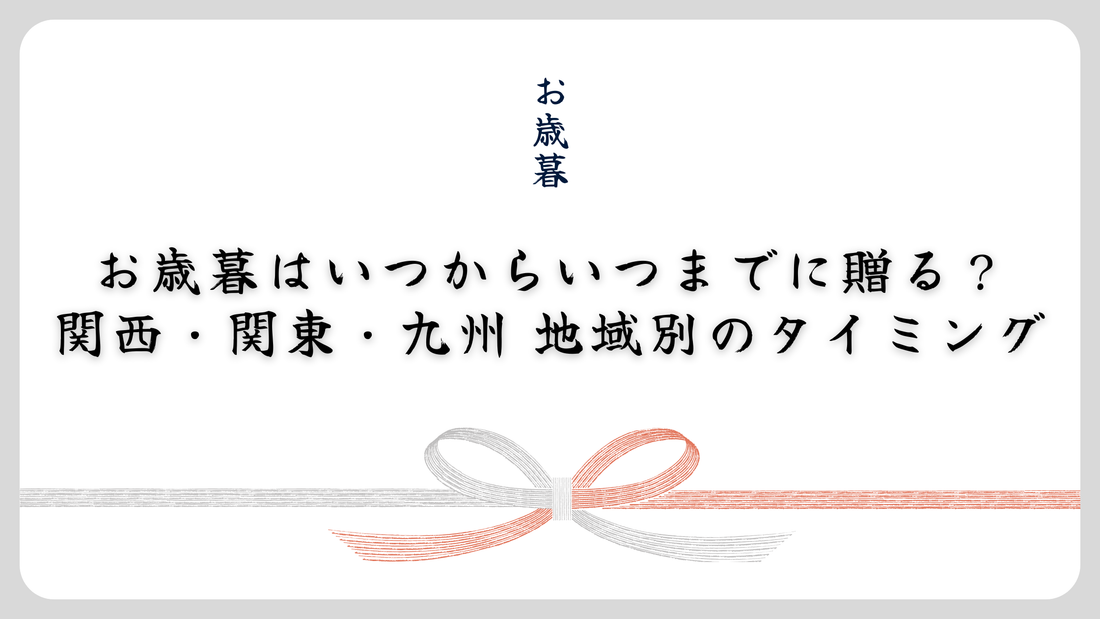
【2025】お歳暮はいつからいつまでに贈る?関西・関東・九州 地域別のタイミング
WANTO編集部
お歳暮は、年の暮れにお世話になった方へ感謝を伝える年中行事。昔は「事始め」とされる12月13日〜12月20日の間に贈るべきと言われていました。現在では前倒しの傾向もありますが、先方の負担を考えれば12月中旬〜20日ごろがもっとも失礼がありません。
なお、「お歳暮」でも通じますが、のし紙の表書きなどの正式な場では「御歳暮」を用いるのが一般的です。
<全国共通>お歳暮を贈る適切なタイミング
全国的な目安は12月上旬〜下旬です。この期間は、年内に感謝を伝える趣旨を守りつつ、繁忙の直前を避けられるため、相手への配慮とマナーの両立がしやすい時期です。
ただし、年末が近づくほど宅配が混み合い、贈り先様の在宅予定との調整も難しくなります。基本は12月中旬に届くよう逆算し、相手の都合に合わせて到着日と時間帯を指定しましょう。特に生鮮・冷蔵品は受け取りやすい平日夕方などを選ぶのが良いでしょう。
冷凍品は、受取後すぐ冷凍の一言をメッセージに添えると親切です。
早すぎても遅すぎてもNG?
11月は季節感が薄く、年末ぎりぎりは先方の片付けや帰省準備と重なります。法人宛ては業務時間内・受領担当が在席の日を指定する、家庭宛ては不在票が残らない時間帯を選ぶ、などの配慮も好印象につながります。
お歳暮の相場
個人向けの相場は3,000〜5,000円、上司・取引先は5,000〜10,000円が目安となります。相手の負担にならない価格帯で、使い切りやすい消耗品(食品・飲料・日用品)がおすすめです。
地域別に異なる!お歳暮の時期【関東・関西・九州】

お歳暮のスケジュールは土地によって微妙に違います。関東は比較的早め、関西は「事始め」以降が中心、九州ほか各地は12月中旬が基本となります。贈り先の地域のならわしに合わせることを最優先にし、戦法が受け取りやすい日取りへ調整しましょう。
遠隔地や離島・積雪地域は配達日数が延びるため、予定より数日前倒しにすることをおすすめします。
それぞれのお歳暮の時期を見ていきましょう。
関東の贈り始めと終わりの時期
関東は動き出しが早く、12月初旬からの手配・中旬着が主流となります。年内でも20日を越えると相手の年越し準備と重なりやすくなります。家庭宛ては平日夜や週末午前の指定、法人宛ては年内営業の最終週(棚卸・大掃除・休業準備)を避けるなど、配達タイミングの配慮が必要です。
関西ではなぜ時期が遅い?
関西は「事始め(12/13)」を区切りに年末行事を整える文化が残り、12月13日〜20日ごろが中心となります。年神様を迎える支度を機に挨拶も始める、という背景が時期感に影響しています。
前倒しし過ぎず、事始めに合わせた到着指定が地域感覚に沿うおすすめの進め方です。取引先には事前に「受け取り可能日」を確認するとスムーズです。
東北・九州などその他の地域の時期まとめ
北海道・東北・北陸・東海・中国・四国・九州は、概ね12月中旬着が目安とされています。積雪や離島便など地域事情で配達日数が延びることもあるため、生鮮・冷蔵品の日時指定は余裕を持って設定しましょう。沖縄など航空便依存地域は、悪天候や繁忙期の減便を見越し、数日前倒しの到着指定が安心です。
お歳暮が遅れた時のマナーと対処法
年内着が難しいときは、表書きを切り替えて気持ちを丁寧に伝えます。元日から「松の内(正月の門松を飾っている期間)」までは御年賀、それを過ぎたら寒中見舞いへ。松の内の期間は地域差があるため、関東は概ね1/7まで、関西は1/15までを目安に、相手地域の慣習を尊重しましょう。
なお、喪中先には御年賀を避け、寒中見舞いで挨拶するのが一般的です。
ここでは、お歳暮が遅れた時のマナーと対処法をそれぞれ解説していきます。
1月1日〜7日までは「御年賀」として贈る
新年の挨拶として贈る「御年賀」は、元日から松の内までが時期とされています。のしは紅白・蝶結び、表書きは「御年賀」、名入れはフルネームが基本です。相手が休暇中で受け取りにくい場合もあるため、在宅予定の確認や時間帯指定を添えるとより親切です。
常温保存できる消耗品(出汁・調味料・タオル等)は喜ばれやすいでしょう。
1月8日以降は「寒中見舞い」として贈る
松の内を過ぎたら「寒中見舞い」へ切り替えます。時期は松の内明けから立春の前日まで。立春は年によって日付は変わりますが、2月の初旬になります。
表書きは「寒中御見舞」、文面は、年末のご挨拶が遅れたお詫び+旧年の御礼+ご自愛の一言を簡潔に書き、喪中先にもふさわしく、落ち着いたトーンを心がけましょう。アルコール・肉類等は差し控えたい品です。
文面・のしの書き方とマナー
のし紙は慶事用の紅白蝶結び。上段に「御歳暮」「御年賀」「寒中御見舞」など表書き、下段に贈り主名を記載します。配送時の破損や汚れを避けたい場合は内のし、進物感を重視するなら外のし。
便せんやカードには100字程度で端的に「旧年中のご厚情に御礼申し上げます。ささやかではございますが御礼のしるしにお届けいたします。ご健勝をお祈り申し上げます。」のように、御礼→贈意→結びの順で整えましょう。
お歳暮の準備はいつから始める?【受付開始時期と計画】
お歳暮の準備は、11月下旬に候補選定、12月上旬に送り先の在宅予定を確認し発注、12/10〜20着を指定する段取りが理想です。相手の好み・アレルギー・宗教上の配慮、会社や官公庁の贈答規程の有無も事前チェックしてください。
人気商品や配送枠は早く埋まるため、早めの計画で品切れや遅延を回避しましょう。二重贈り防止のため、家族・部署内でリストを共有し、昨年の実績や好評だった品もメモしておくと来年が楽になります。
デパート・百貨店の受付はいつから?
多くの百貨店は11月〜12月初旬に受付がスタートします。早割や送料無料のキャンペーン枠、指定日の空きは先着で埋まってしまうため、早めのリサーチが鍵となります。店頭受け取りと配送の使い分け、複数宛先の一括管理、ギフト包装・のし設定の一括指定などで手配を効率化しましょう。
また、法人宛ては社内規程や受領フロー(総務受付・納品書必要・領収書宛名)を必ず確認しましょう。
オンライン通販の受付開始時期と配送日指定

ECサイトは受付が早く、選択肢も豊富です。ただし、到着日は相手地域の慣習に合わせるのがマナーです。年末は天候・交通事情で遅延が起こりやすいので、希望日の2〜3日前倒しで指定し、時間帯指定・置き配可否・不在時の再配達手順・追跡番号の共有までセットで手配します。
到着日当日に受け取れない可能性がある先には常温品を選ぶと安心です。環境配慮を重視する場合は、簡易包装・紙素材の選択や、産直のエシカルギフトも喜ばれます。
準備をスムーズに進めるコツとチェックリスト
1)贈る相手/住所/在宅日時を確認
2)品目と価格帯を決定(アレルギー・宗教配慮、アルコール可否)
3)のし種別・表書き・名入れを設定(内のし/外のしの選択)
4)到着日・時間帯を指定
5)配送方法(常温・冷蔵・冷凍/クール便)を選択
6)メッセージカードを用意(御礼→贈意→結びの順)
7)注文控え・追跡番号を共有(家族・部署での二重贈り防止)
8)受け取り確認の一言(「お手元に届きましたらご笑納ください」など)
9)辞退の申し出があった場合の記録(以後は年賀状・寒中見舞いへ切替)
まとめ|お歳暮の時期を守って、心のこもった贈り物を
お歳暮を贈る時期の基本は12月中旬〜20日ごろ着です。
相手地域のならわしに寄せ、在宅や保存性に配慮して手配すれば、気持ちよく受け取っていただけます。もし年内に間に合わなくても、御年賀・寒中見舞いへ切り替えればOK。
のし・文面・配送まで心配りを重ね、「今年もありがとうございました」の想いがまっすぐ伝わる、気持ちのよい年末のご挨拶にしましょう。












